新着情報
what’s new
-
パートナーの浮気を弁護士に相談すべき5つの理由とボーダーライン
パートナーが浮気をしている事実を知り、弁護士に浮気の相談をすることをおすすめします。弁護士に相談することでパー…
探偵フランチャイズの
新モデルを確立
探偵フランチャイズNo.1の第一探偵グループ
探偵FC詐欺の撲滅
を目指します
探偵業に憧れて独立開業をお考えの方も少なくないと思います。私自身も夢見てとある探偵FCに加盟して開業をしました。しかし、現状は説明会で聞いた話とは全く違い、加盟店のほとんどが仕事がなく開店閉業状態で、開業しても1年で廃業に追い込まれるのが大半でした。その原因はその探偵FCには「WEB集客ノウハウ」が一切なく、高額なアナログ広告への出稿を余儀なくされたからです。
その経験から第一探偵事務所では「アナログ広告」を廃止し、費用対効果が高く一度の対策が資産として残る「WEB集客」に力を入れています。
第一探偵FC本部による集客サポート

①SEO対策代行
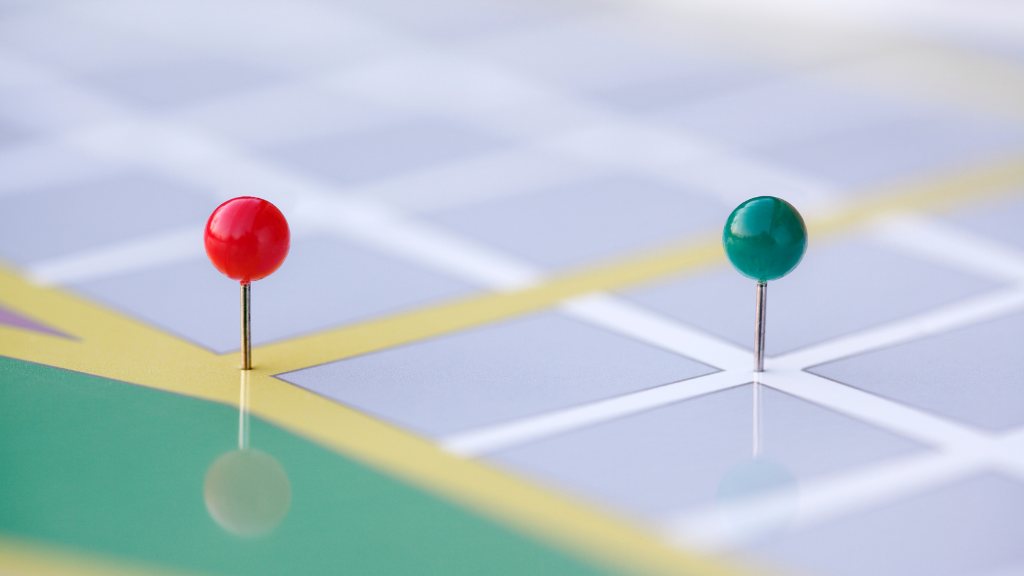
②MEO対策代行

③広告業者との価格交渉

なぜ探偵業での開業は
失敗が多い?
探偵業界の真実
市場が小さく競争が激化
探偵業の市場規模は800億円程度しかなく、いわゆるレッドオーシャン。
大手直営店の高シェア率
アフィリエイト広告と提携している大手直営店に資金力では勝てない。
FC募集元による誤認勧誘
WEB集客ノウハウが乏しく、全く儲かっていないFCが募集している。
第一探偵グループの加盟店サポート体制
SEO対策代行
サポート
開業時はFC本部がホームページ制作を代行。不倫・浮気調査で集客できるようにSEOを意識して制作いたします。制作後はFC本部がコラムの作成やページ更新などの内部対策、外部サイトから被リンクを集めるなどの外部対策を実施していきます。
MEO対策代行
サポート
FC本部が加盟店様に代わり「Googleプロフィール(Googleマップに表示される自社情報)」にキャンペーンや新着情報を投稿するなど内部対策を代行します。また同時にサイテーション対策や良質な口コミを集めるなどの外部対策も行います。
広告業者との
価格交渉
第一探偵事務所では「Googleリスティング広告」等をグループ一括の申し込みを検討することで、広告業者と価格交渉が可能です。FC本部がキーワードプランナーの予測データから費用対効果が高いと思われる広告のみを選別してご案内します。
第一探偵事務所の強み
FCでも選ばれる特長
1店舗あたりの指名検索No.1の探偵事務所
第一探偵事務所は全探偵フランチャイズ内で「Google知名度(指名検索数)」はグループ全体ではNo.2、「1店舗あたり知名度(指名検索数)」ではNo.1の探偵事務所です。全加盟店舗が開業1年目から黒字経営をしています。
探偵FCで人気の理由

業界最安値の加盟金

案件紹介率90%超え

大手弁護士事務所との提携
第一探偵グループが
FCで人気の理由
探偵業で最安値
の加盟金
第一探偵事務所ではFC加盟金を最安値水準で設定しています。その理由は余裕のある資金は、ご自身の集客に必要な広告費やテナント代に回していただきたいからです。全加盟店が1年目から黒字経営ができるように全力でサポートしています。
案件紹介率は
業界最高水準
第一探偵グループは探偵FCで最高値の案件紹介率90%を誇る探偵事務所です。理由はFC本部が集客代行を全て代行していることに加えて、グループで同業他社様や法律の専門家との業務提携をすることで案件が舞い込んでくるからです。
大手弁護士事務所
との業務提携
第一探偵グループでは探偵フランチャイズで’唯一’大手弁護士事務所と提携をしております。お客様からアフターフォローで選ばれやすくなるだけではなく、全国に支店のある大手弁護士事務所様から証拠を必要としている顧客をご紹介いただけます。
相談から契約
STEP
開業希望地と市場調査
ご希望の開業地と市場の需給をGoogleから提供される公式データから分析し、開業の可否を決定します。

STEP
集客に有利なテナント探し
地域の集客で有利になるテナントをピックアップします。予算から最適な選択を後押しします。

STEP
契約書の取り交わし
開業後に失敗が少ないと思われる条件が整いましたら、『FC契約書』を取り交わします。

よくあるご質問
-
探偵業は儲かりますか?
-
とても微妙なところです。探偵依頼は集客ノウハウや資金があるところに集中します。つまり、依頼がある一部の探偵社はとても儲かり、ノウハウやが足りない探偵社には全く依頼がありません。ランニングコストが低く利益率が高いという意味では儲かると言えるのかもしれません。
-
副業でも可能ですか?
-
第一探偵事務所のフランチャイズでは、FC本部が加盟店様に代わり集中活動を行っていますので可能です。一般的な探偵社では、生活の為に副業を始めると集客活動(SEO対策等)に時間が回らなくなり、さらに問い合わせにも対応が遅れることから悪循環に陥ることが多いです。
-
探偵業の資格を取得すると集客に有利ですか?
-
探偵業の資格があっても集客に有利になることはほとんどありません。但し、探偵の資格を与えている経営母体の地位向上があれば状況は変わる可能性はあります。
-
探偵学校に通ってから開業した方が良いですか?
-
全くそのようなことはありません。探偵学校で学べるようなことは、第一探偵グループの研修でも学ぶことができます。
代表挨拶
Greeting
探偵業をFCで始めようと複数の探偵社に話を聞いた方は、結局どこが良いのか分からなくなっているかもしれません。
そのような状況は、実は探偵に調査依頼を考えている人達には常日頃から起こっています。結局どこに依頼して良いか自分で判断できず、事実とは違う集客の為に作られた広告やおすすめランキングを鵜呑みにした結果、探偵業者とのトラブルに巻き込まれてしまうケースが後を絶ちません。
第一探偵事務所では、このような業界の悪しき慣習を変えることを目標に活動をしています。そのため、第一探偵グループのご加盟者様には本気で『地域でNo.1』を目指していただきたいと考えています。
第一探偵グループのFCで成功するために必要なのは、広告資金や集客ノウハウではなく「人の心の痛みを分かろうとする姿勢」です。
第一探偵事務所
グループ代表 佐藤翔吾
事務所概要
Office
| 会社名 | 第一探偵事務所 |
| 代表 | 佐藤翔吾 |
| 届出書の受理番号 | 宮城県公安委員会 第22180018号 |
| 店舗数 | 9店舗(2024年3月時点) |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10‐3 JMFビル仙台01 2F |
| TEL | 050-5468-0361 |
| FC資料 | FC資料ダウンロード |
全国の支部一覧
FC本部へのアクセス
Access
- 所在地
宮城県仙台市中央4丁目10‐3
JMFビル仙台01 2F - 電車でお越しの場合
JR仙台駅「南出口2」から徒歩3分 - 営業時間
24時間 / 年中無休

